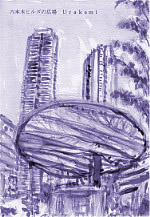| ヨシュアの作業場 |
 |
浦上氏は応仁の乱の後、管領赤松氏に逆らって、播磨・備前を支配したが宇喜多氏との攻防に負けたこと。
その出城の一つの土塁がこの絵の右手の高台。私の実家の真正面。石が積んであってへんな畑だなと思っていた。
正面の小屋は木工を業とする方の作業場。その方はそれもあって信仰上ヨシュアと命名を受けているらしい。
|
| 烏城(岡山城) |
 |
熊本城と似る。烏城は外観の黒さからの通称。 私の生家は戦国時代の播磨、備前を支配していた浦上氏の出城の一つ、多分島村弾正という家来の掘城という平城の土塁の数十メートル山側です。隣は島村姓で
す。浦上氏は家来、宇喜多能家が切れ者すぎて恐れをなし暗殺した。後に辛酸をなめた子の直家に滅ぼされ、その子秀家は秀吉の寵愛を受け、西の大川(現旭
川)の流れを変えて掘となす豪勢な城を建てたが、関ヶ原で敗れ、池田氏の城となったという転生を辿る。秀家は、八丈島に遠島、家光の代まで生を得たとい
う。(津本陽「宇喜多秀家」に詳しい。) |
| 犬吠埼 |
 |
ここの絵は構図も何も要りません。関東の画家はここをよく描いているようですね。竹久夢二が愛人連れで逗留していたと言う宿の海岸で。夢二といえば、岡山
県邑久町出身、私は邑久高校卒。でも、ちょっとタイプが違うね。大正ロマンの夢二さんがただ荒いだけの海を見て何がよかったのか?よくわからん。
|
| 三沖の見晴台 |
 |
実家のある隣村の裏山を正月に登る。遠くに新幹線が走る。私の家も弟の家も見える。大きな山は熊山。熊山は私の中学校の一日登山の山。山上には解明されて
いない石積遺構(国指定史跡)がある。熊山町の常念寺には隠遁した、室町幕府八代将軍足利義政の正室日野富子(ひのとみこ)の墓がある。東大平山、西大平
山と連なる。 |
| キャンプ場 朝 |
 |
黒田庄町のキャンプ場の朝 牛と共産党員町長(牛と並べてゴメン?)で有名です。真夏のテントの寝床は灼熱の火照りを背中に感じるのですが、さすがに朝方には冷めた。小さい男の子が二人。早くも起き出してくちゃくちゃ話してる。
|
| 土浦城址 |
 |
茨城県というのは「何か用事がなければいくことないね」と言いながら勉強会に参加した時のものです。
土浦では亀城公園で絵を描きました。土屋氏が明治まで、あ、土浦日大の土屋と江川の名勝負があったなとか、違う土浦日大は工藤、土屋は銚子商業だとか、現場に来るといろいろ思い出します
|
| 三ノ宮センタープラザより |
 |
三宮の駅の浜側の東天紅という中華料理屋さんで会合があった。耳だけそっちへ向けて、堅いボールペンで線を書いて色鉛筆で彩色した。向こうに見える人工島や泉州沖。この狭間にこの上、神戸空港が入ったら、空間がなくなるやんか?息苦しすぎですよ。
|
| 六本木ヒルズの広場 |
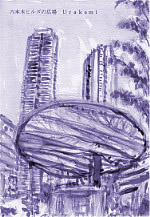 |
これは、例の回転ドア挟まれ事故のわけのわからん巨大ビル前。
向かいの朝日テレビとの共通スペースの広場でマニュアル嬢の売るコーヒーを飲んだ。大きな二つのビルは、麻布の億ション。ここの人工の浅い池にメダカがいるのですが、取らないで下さいとしつこく書いてある。何でも人工だからメダカも作っているんじゃないかと思ったよ。
|
| 鞆の浦 |
 |
桟橋におおかた20人位の絵描きの団体が並んでこのあたりを描いていた。絵になる風景なんでしょうね。私は向かいの仙酔島にわたる船待ちの時間にガサガ
サと。映画のロケでここを走って手を振るシーン。よく見るでしょう。あの常夜灯は現存する日本でもっとも高いのだそうです。幕末のままの家が沢山残ってい
るところ。源平合戦、村上水軍の拠点、足利尊氏が後醍醐天皇に対して挙兵した港、信長に追われた足利を毛利がかくまい幕府再興を野望?なんて京に対抗した
西国の歴史の舞台なんですね。 |